■■■お知らせ■■■
関係各位、並びに顧客の皆様、
いつも大変お世話になっております。
2017年7月6日〜17日の間、エム・レコードの事務所・倉庫移転に伴う諸作業のため一時的に商品発送を休止致します。通常発送の再開は7月18日を予定しております。受注はいつも通り受け付けております。
皆様には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
エム・レコード
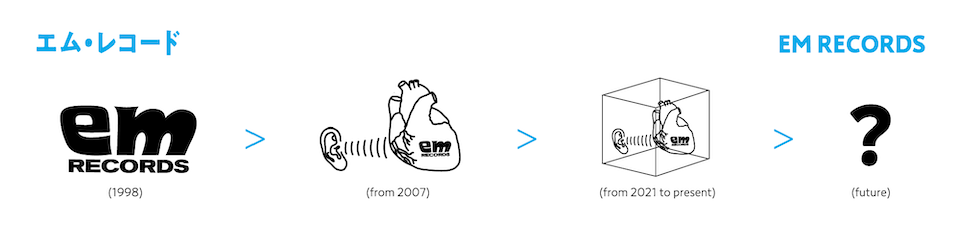
■■■お知らせ■■■
関係各位、並びに顧客の皆様、
いつも大変お世話になっております。
2017年7月6日〜17日の間、エム・レコードの事務所・倉庫移転に伴う諸作業のため一時的に商品発送を休止致します。通常発送の再開は7月18日を予定しております。受注はいつも通り受け付けております。
皆様には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
エム・レコード
話し手:富田克也(空族)、相澤虎之助(空族)
聞き手:江村幸紀(エム・レコード)
「早くも2017年日本映画のベスト・ワンに遭遇?」(キネマ旬報)と話題にのぼる『バンコクナイツ』の待ちに待った関西初上映初日(4月1日)、シネ・リーブル梅田に舞台挨拶に来られた空族の富田・相澤両監督に取材を行った。昨年から空族の様々なインタビューが紙面やネットを賑わせているが、『バンコクナイツ』の音楽面について焦点をあてたのは今回が初。音楽好きの方も楽しめること請け合いのインタビューだ。
始まりは「田舎はいいね」と「イサーン・ラム・プルーン」だった
――『バンコクナイツ』は音楽でも評判になっています。菊地成孔さんが『CULTURE Bros.』で「職業音楽家として聞いても素晴らしい」と仰っていたのがすごく嬉しかったです。いわゆる音楽映画ではないんですが、それに近いものになっていて、3時間の映画で音楽が実は3分の1流れています。これは偶然ですか?意図ですか?
富田「これはもう撮る前からこの映画は音楽だらけになるだろうという予想はしてて、その通りになりましたね」
――音楽の付け方について、この曲を使いたいと思った第1号はなんですか?
富田「ディー・テーテーですね」
――「田舎はいいね」ですね。
(※「田舎はいいね」はルンペット・レームシンが歌うルークトゥン曲の題名で、富田監督の言う<ディー・テーテー>は印象的な歌い出しの部分を指している)
相澤「僕は「イサーン・ラム・プルーン」だったですね」
(※「イサーン・ラム・プルーン」はアンカナーン・クンチャイが歌うルークトゥン・モーラムの大名曲。映画のエンディングで使用された。ちなみに劇中でエディット無しのフルコーラスで使用されたのはこの曲と「田舎はいいね」の2曲のみ)
富田「ディー・テーテーは割と早めに発見したんですね。この曲、コンピレーションで聞いちゃったんですけど、それからずっと、絶対にディー・テーテーを使おうと思って」
――「田舎はいいね」はタイ語がなんとなく分かってきたときに聞いたんですか?
富田「ディーは分かる。「良い」ってことですけど、テーテーが分かんないから、それで周りのタイ語できる人に聞いて、これ何ていう意味なんだろうねぇ?とか言って、ああ、田舎はいいねって話なんだなあ、こっちはいいよ~って歌ってることが分かって、バッチリだ。だから、ノンカーイ(※タイ東北部の地方都市)に突入した瞬間に、あのショットでこの曲をかけるってのは、もう一番最初に頭に浮かんでて、その次がたぶんね、あのアンカナーン・クンチャイ「イサーン・ラム・プルーン」じゃないかなぁ。あれ?逆だっけ?笑」
相澤「俺は「イサーン・ラム・プルーン」じゃないかなぁと。時系列ではね」
富田「そおだったかなぁ~?その可能性も……ある。笑」
相澤「忘れちゃったなぁ、どっちが早かったかなぁ~」
富田「「イサーン・ラム・プルーン」は聞いて一瞬で気に入ったんだけど、どこで使おうかっていうのは少し迷ってて、後で決まったと思う」
――今の話を聞くと、映像イメージがまずありきで、そこに付ける音楽を探していたという風に取れるんですけど。
富田「はい」
――そのプロセスが気になって。曲を聞いて映像イメージが浮かぶ場合もあるのか……。
富田「最初は曲聞いて、うわっ、いいなぁ~、どっかで使いたい、でもどこだろう?で、歌詞を聞いたら、つまり「田舎はいいね、こっちはいいよ」って内容だった。なるほど、じゃあ、ノンカーイ・パートに入る、田舎に入るところで使おう、と」
相澤「曲の方が先だったよね?」
富田「曲の方が先」
――歌詞内容は要するに田舎賛歌ですね。ルークトゥンの王道のテーマ。
富田「その後、ロケハンして旅をしていく中で、あのショットの、あのノンカーイ、あの風景の場所に付けて、ああっ、ここで、あの曲がバ~~~ンっ、バンっ、バンって始まるという」(※この「バ~~~ンっ、バンっ、バン」はイントロ伴奏のリフを表現していらっしゃいます。念のため)
――説明しておくと、空撮のところ。ゆったり空から降りて行くシーンの事ですね?
相澤「メコン川を見下ろして」
――空族初の空撮。
相澤「そうです、そうです(笑顔)」
富田「バンコク・パートからノンカーイ・パートに入る」
――田舎と都会の区切りの象徴ですね。
富田・相澤「そうです!」
――試写の段階で「あの曲は何だ。あの曲が欲しい」とみんなに聞かれて、その時はまだサントラ制作は決まってなくて、「これは……まだ分からないんです」と答えるのが悔しかったですね。さて、この「田舎はいいね」と「イサーン・ラム・プルーン」に惹かれた理由は何ですか?
富田「う~~ん(考え込む)。やっぱ、こう、ああ、俺はほんとはこういうのが好きだったぁ~って、思ったんです」
相澤「とんでもない感じでしたよね。要するに自分たちが今まで聞いてた音楽の上を、何か、ワーっと、そこにブッかぶさって来たっていうか。そういう感じの体験。だから、例えば、第一印象いわゆるファンキーな曲だとか思うけど、今まで聞いてきたファンクとかレゲエと違う、聞いたことない曲だったんですね。そういう中でも記憶にはない曲だけど、感覚では分かるっていう曲だったって感じだった、みんなで聞いた時は」
富田「あの~、一応、僕、元々はバンドをやりたくて東京に出たって事になってるんすよ。経歴上だと。笑」
――オザワではなく?
富田「オザワでなく富田です。高校を卒業してバンドをやりたくて上京っていうプロフィールだったんです。あの頃(※90年代初期)、普通に田舎の少年がバンドやりたくてって時代だったから。ロックというものを中心に僕の音楽が形成されてるわけです。それでほら、パンクやニューウェーヴとかかじったんですけど、虎ちゃんが今言ったように、色んなものが少しずつ入っていますよね。例えば、レゲエの感じとか、ロックのこんな感じとか入ってたんですよね」
――音楽が大好きですよね。
富田「いやいやいやいや。そうしといてください、じゃあ(笑)。そこまでじゃないですけど。それで「田舎はいいね」にしろ、アンカナーンさんにしろ、最初に聞いたとき、あぁ、理想としている音楽が全部入ってる!」
――ビリビリ感じた?
富田「はい。あああぁぁ~っていう。それまで聞いた事ないんだけど、そこになんとなく自分の理想みたいなものが全部あって。それは音質の事も含めて。古いあの感じの録音とか。最初はレゲエみたいに感じた。歌詞の内容もそう。自分の思ってる理想の音楽みたいな気がしたんですよ」
『バンコクナイツ』音楽の三本柱
――映画の音楽担当は山﨑巌さんとYoung-G(中村誠治/stillichimiya)ですよね。この二人の起用はいつ決められましたか?
富田「それは最初っからですね。これまで映画作って来た流れで、今回も山﨑さん率いるバビロンバンドにやってもらう事になるだろうし、Young-GにはEDMを中心に作ってもらう事になるだろうと思ってました。そこに加えてタイの音楽にも出会えた。三本柱ですね」
――一本目は山﨑さんとバビロンバンド。二本目がYoung-G。三本目がタイ、ですね。Young-Gが作る曲は、僕からすると現代性を加えている点が重要で。そして、山﨑さんですが『バンコクナイツ』に一番多く登場するのがバビロンバンドの曲です。これらは以前録った音源を使われたそうですが、何だったのでしょうか?
富田「『バビロン2ーTHE OZAWAー』のサントラからです」
――『バビロン2ーTHE OZAWAー』の音源をなぜ再び持ってきたんですか?既に出たサントラ曲の再使用ってのは聞かない話です。
富田「『バンコクナイツ』と『バビロン2』は姉妹作品なんです。元々、自衛隊員のオザワってキャラクターは『バビロン2』で初登場するんです。そのオザワが『バンコクナイツ』にも引き継がれる事になったので、意図的にダブらせました」
――これは重要です。その辺り詳しくお願いします。
相澤「『バビロン2』の話から言えば、僕が東南アジアを旅した経験から作ったものですけど、向こうのちょっとしたバーとか、バービア(※ピンクに光ってる屋台形式のガールズバー。タイに無数に点在)に行ったりするとですね、白人の人たちがロックを聞いてる、やっぱり。昔の世代の、CCRだとか、その昔のベトナム戦争時代の曲がほんとに流れて来るんですよね。そういうのって実はアジアの一風景で、ああいう風な感じを生み出しているのが60年代の音楽だったり、ロックだったり。でもそれは実際、僕らの映画には使えないわけです(※ライセンス料が高額なため)。だから、そういう60年代ロックの雰囲気で作ってくれって僕たちが山﨑さんに頼んだんですね。それがバビロンバンドだった」
富田「実際、ノンカーイのバービアにね、白人のオッサンたちが飲みに来るわけ、毎晩、毎晩、溜まってるわけ。今、みんなYouTubeだから。バーでかける曲も、スピーカーつないで、パソコンのところ行って、ジュークボックスみたいにYouTube選んで、白人のオッサンたちに任せておくとそれこそCCRとかねぇ、80年代ヒット曲とか」
相澤「90年代までとかの曲をやっぱりかけるんですよ」
富田「俺達はそこでカラバオとか、カラワンとかを流す(笑)。だんだん、俺達の音楽知識が増えていくことによってルークトゥンとか、モーラムとかをかけちゃうわけですよ。そうっすっと、白人のオッサンたちがそんな曲かけられても、まったく面白くも何ともねぇよって顔で、曲が終わったとたん、すぐCCRとかに戻す。このせめぎ合いをね、日夜やってたんですよ、向こうでね。笑」
(※カラバオ、カラワンは通称プア・チーウィット(=生きるための歌)と呼ばれるタイのジャンルの代表バンド。共産主義~左傾の歌詞で知られる。バービアにたむろする類いの人間を痛烈に批評する歌が多い)
相澤「笑。毎晩やってたね」
富田「『バンコクナイツ』でもね、ノンカーイのスマイル・バーのシーンで、その曲の変えっこを実はサラッとやってるんですよ」
相澤「そうね」
富田「店で働く女の子が選曲したと思われるカラバオの曲を白人のオッサンが変え、そこで流れてくるのがバビロンバンドの曲っていう寸法でした。分かりにくいとは思いますが。笑」
――後半のオザワのシーンでバビロンバンドの「Song of an Angel」が、50年代調のいわゆる三連のロッカ・バラードの曲が入るんですけど、この選曲が拍子抜けする感じがして、逆にすごいなと思ったんですよ。通常の映画の進行だったらクライマックスがあり得る絵で、緊張感がグッと来るところで、あの拍子抜けのロッカ・バラードが来た。そのセンス。誰が決めたか?
富田「僕なんです」
――コレだって決めてあったんですか?
富田「元々、あの曲も『バビロン2』でかかってるんですね。『バビロン2』では最初にかかる曲がアレなんです。レストランのステージでベトナム人の歌手が歌っているシーンにバビロンバンドが付けた曲です。だから歓声と拍手が入れてあるんです。オザワのところに付けると拍手と歓声で迎えられてるみたいで面白かったので。これだなと。江村さんが仰ってくれたように、拍子抜けしてるくらいでちょうどいいなと思ったんで、いろいろ嵌った感じでした。そもそも、あの曲を山﨑さんたちにオーダーしてるのは虎ちゃんなんですよ。『バビロン2』のとき」
相澤「あれは、そう、ロージー&ジ・オリジナルズ(Rosie and the Originals)ってアメリカのバンドに「Angel Baby」ってのがあるんですけど、アレのパクりを作ってくれって頼んだ曲なんですよね」
富田「それでほら、『牯嶺街(クーリンチェ)~』の……」
相澤「ああ、それからあの、エドワード・ヤン監督の『牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件』っていう映画で、登場人物でリトル・プレスリーってのが出てくるんですけど。その子供が歌うんですね「Angel Baby」を」
――やられた!これはもう最高のオマージュと引用です。
富田「実は、僕はこの映画を何回も見直して来たけど、今まで『牯嶺街~』に出てくるメロディーは英題にもなっている、プレスリーの曲の方しか残ってなかったわけです。でも、虎ちゃんはほんとにサラッとしか流れない「Angel Baby」が記憶に残ってたから。なかなか憎い(笑)」
――そういえば山下達郎さんにもロージー&ジ・オリジナルズへのトリビュート曲があるんですよ。「おやすみロージー」だったかな。
相澤「マニアック……」
DJ KENSEI、Tondo Tribeとの知られざる交流
――さて、あのKENSEIさんが曲を提供されてますけど、タイでの撮影中にKENSEIさんが現場を表敬訪問されて生まれた話だと聞いています。
富田「そうですね」
――曲の採用はその場で決めたんですか?
富田「いや、その時は撮影で夢中になってて、KENSEIさんによくよく挨拶もせず。KENSEIさんは遠慮がちに後ろの方で見ててくださってました。「あの~、じゃあ僕これで失礼します」「あっ、帰っちゃった!」みたいな感じになっちゃって(苦笑)。その時はお話できなくて。撮影を終えて一息ついてたら、Young-Gが「KENSEIさんがこれだけのトラックを預けてってくれたんすよ」って、その直前までイサーンやラオスを旅しながら作りためたスケッチのようなトラックたちを聞かせてくれたんです」
相澤「『IS PAAR』を作ってる時ですね」
富田「当然まだCD発売の前でしたが、ポンと置いてってくれて。で、そしたらケーンの音は入ってるし、これから僕らが撮影で向かおうとしている方角からの音がたくさん響いてくるんです。予感のようでしたよ。完全にリンクしてましたね」
――KENSEIさんですが、エム・レコードで既に出ていたんすよ。ALTZ(アルツ)って大阪のアーティストがいるんですけど、彼に発注したアルバムにDJ KENSEIがフィーチャリングされてて。なにか、因縁めいたモノを感じました。
富田「『バンコクナイツ』で2曲、KENSEIさんの曲を使わせて頂きました。ひとつは「Khane Whistle」と、もうひとつは「「Vang Vieng Bank (Change Yen to Lao) 」。あれが見事にラオスのバンビエンで作られた2曲で、まさに劇中のラオスシーンにピッタリと嵌りました。というか、僕ら撮影隊がバンビエンに到達したら全員の頭の中では既にこの2曲が鳴り続けているくらい、その後KENSEIさんのビート集を聴きまくってましたね。遡っていく感じでした」
――その曲がラオス録音って分かってました?
富田「はっきりとは。でも、KENSEIさんの道のりが、そのまま俺達の現場になっていくので、その土地に行って聞くと一致するわけですよね。自分たちがその場にいる感覚にKENSEIさんも触れているわけで、そこで作った曲がやっぱりスッと入って来る」
――それで腑に落ちました。KENSEIさんが入って来るのは、どういう経緯だったのか興味があったので。
相澤「別にこっちからお願いしたわけでもないし、KENSEIさんもそうだったと思います。やっぱり運命的に旅が重なってたんですね、KENSEIさんと」

Tondo Tribe, Young-G, 田我流 ©Bangkok Nites Partners 2016
――KENSEIさんから派生するんですけど、トンド・トライブ(※フィリピンのヒップホップ・グループ)の起用は事情を知らないと唐突感が否めないですが、これは誰のアイデア?
富田「俺と虎ちゃん二人で。あのラオス・パートには、とにかく今まで関わった仲間達を全員終結させたい、っていう狙いがあったんですよね。んで、トンド・トライブは『サウダーヂ』が終わって、確か1年、いや2年経ったくらいかなぁ~。たまたま誠治(Young-G)から夜中、電話かかってきて「ヤバい話きましたぁ~。マニラのトンド地区っていうのがあって、知ってますぅ?」って。「まさか、あの有名なヤバい街か?」って。東南アジア最大のスラムの」
――商店が檻というか金網で囲われてて、商品受け渡す場所がこれくらい(15cm四方)しか開いてないとか、ですよね。すぐ強盗来るから。
相澤「そう、そう、そう」
富田「で、誠治が「そこに入り込める話っす」って。ワークショップやるんだと。つまり、国際交流基金がスポンサー、スラム地区にいる少年少女たちを、つまりその、ヒップホップで自立させる、そういう音楽に触れるっていうワークショップ」
相澤「そういうプロジェクトがあったんです」
富田「stillichimiyaのトラックメーカーであるYoung-GとBig Benのおみゆきチャンネルっていうクルー内ユニットが呼ばれたんです」
――知らなかった!おみゆきチャンネルがワークショップとして行った?それはちょっと色んな意味で危険でヤバイです(笑)。何年ですか?
富田「2012かなぁ~」
――その時にトンド・トライブと交流したんですね。
富田「したんです。トンド・トライブとおみゆきチャンネルでアルバムとMV作ろうって流れ。ドイツからは黒人のプロデューサーと、中米系のダンサーが来ました。このダンサーの彼の父親はMS13(※中米最大のギャング・グループ)の創始者メンバーのひとりだと言ってました」
――これでトンド・トライブの登場に合点がいきました。アジアン・ミュージックって言い方は好きじゃないんですけど、アジアに分散している点と点が映画上で繋がって線になるっていう示唆的なシーンだと思いました。
富田「誠治がそう言った時に俺達も行きたくなったんですよ。そんなチャンス滅多にない。毎日、銃撃戦が起きちゃうような場所だから、よっぽど何かないと入り込めないだろうと。で、空族がそれをドキュメンタリーとして撮影するので、俺達も同行させてもらえるよう誠治に頼んで交渉してもらったら、「行けるっす、監督!」みたいな感じで。で、俺と虎ちゃんと助監督の河上健太郎の3人で空族として参加して、おみゆきチャンネルと5人で乗り込んで、トンド・トライブと2週間びっちり、ずっと一緒にいたから、めっちゃ仲良くなって」
相澤「フィリピンはヒップホップが物凄くて、盛んなんですね」
富田「歴史も古く」
相澤「古いんすよ、アジアで一番、古いから」
――英語圏だから根付きやすいですよね。
富田「そー、そー、そー」
相澤「逆にその~、だからYoung-Gとか、いわゆる<アジアのヒップホップ>という物に目覚めたと言うか」
富田「そうそう、だから、この企画におみゆきチャンネルを選んだ国際交流基金はよくみてるなと思いました。そして、トンド・トライブも本当に凄かったし」
相澤「こんなに凄いんだぁ~みたいな。モロで見てたから、フリースタイルにせよ、何にせよ。そういうところで僕たちも彼らの音楽に物凄いビックリしたし、彼らは彼らで真似モンじゃない物を構築しようとしてるってのがあったから、これは!って事で」
富田「そこら辺の屋台で物凄いブートをぶわぁ~って売ってるわけなんですよね、タイと一緒で。Young-Gもそこでハマって、山ほどディグって帰ったわけですよね。あいつの「PAN ASIA」シリーズはそこから始まったんじゃないかな。それで「PAN ASIA」でフィリピンだけじゃなく、いろいろ掘り始めたらタイのヒップホップも引っかかるだろうし」
――中村君(Young-G)、アジアン・ヒップホップ詳しいんですよ。なんで知ってんのかなぁと思ってて。
富田「それが大きかったのは間違いないと思いますよ。それでトンド・トライブとはその後、付き合いが続いているんです。リーダーのシルバートは、そのワークショップの日本版が開催されたときに来日もしまして、山梨にも連れていきました」
占い師サイの名シーン誕生の裏には
――次の濃い話ですけど、みんなの脳裏に焼き付いて離れない、あのアンカナーン・クンチャイが演じた占い師のシーンについて。アンカナーン出演のアイデアはいつ芽生えましたか?
富田「Soi48と出会ってからですね」
――Be-Waveでやったアンカナーンさんの初来日公演とタイ音楽講座に、実は両監督で来てたんですよね?Soi48と僕の3人でやってて、あの時が東京編の第1回でした(※先に2回大阪でやっていた)。知り合った後になってお二人が参加していたと知らされて、僕らも二重で驚いたっていう。あれ以降なんですね。
富田「もちろん、ご本人を目の当たりにしたっていう事があって、ただ、その時は僕らアンカナーン・クンチャイって言われても、何にも分からないで行ってますから。そこで、あのCDを買ったわけですよ。『イサーン・ラム・プルーン』を(※エム・レコードより発売中♡)。それで帰ってパカって再生して。わぁ~~~~っ!これもう絶対使いたい!とまず思った。で、そこからこうずっと頭に残り続けてたけど、まさか、出演してもらうなんて急にはちょっと。でも、よくよく考えて、これ、Soiに相談すりゃ、なんとかなんじゃねぇか!?みたいな事をある時から言い出したんですよ」
相澤「映画後半で、占いおばあさんって役が出てて、それで、その時に顔が出てきたんです」
富田「そう、これ誰にやってもらう?もしかして、アンカナーンさんがこれやってくれたらヤバい事になるんじゃねぇか説が出始めた。で、恐る恐るSoi48に聞いたら、物凄く軽~く「いや出ますよ~」「嘘だ~!」なんつって。(軽い口調で)「いや、全然イケると思いますよー」って(一同、笑)」
――その話ですけど、プロとして興行をされている方なんで、その出演オファーを聞いても、まぁ大丈夫でしょうって僕らでは言ってましたよ。で、噂ではあの重要シーンの撮影が一発OKだったと。
相澤「一発OK。動じず、微動だにせず」
富田「じゃあ、そろそろ、よーい、パチンってやって。スーっとこちらを向き直ってそっからのアレ(※ラックを癒す祈祷シーンのこと)でした。みんな固唾をのんでねぇ。3カメ置いて。まず、正面の引きと、ラックのアップと、そして、アンカナーンさんのアップ。構えて、よーい、スタートして。ほんで、一発。最初あっけにとられちゃって。それでようやく、あっ、OKっでーーす、みたいな。改めて、おおおおお~!って」
相澤「一瞬ね、持ってかれてましたよ」
富田「カットするの忘れてた」
――あのシーンを映画館で見た女子達、泣いてましたよ。名シーン。
相澤「あのラムは主演女優のジョイ(=ラック)も泣いたんです」
アピチャートポン熱く反応
――では、最も難しい部分に。チット・プーミサックの詩をカラワンのスラチャイの亡霊が話すシーンは、非常に皮肉で、意図したかどうかは別として、タイの非常に複雑な部分を奇しくも描けたと思います。このアイデアは、元々、誰から出ましたか?
相澤「僕です。それはあの、僕たちはそのタイの今の政治状況が分かんないから、ただ、チット・プーミサックの亡霊が出るって事は決まってたわけです。シナリオで。それを誰にやってもらうかっていう部分でした。スラチャイさんはカラワンでプーミサックを歌ってるし。それで、物凄いレジェンドみたいな人っていうのは分かってるわけで。それでもね、俺、アンカナーンさんがOKって言ってくれたから、ひとりくらい行けるんじゃないかなぁ~と」
――順序がそうだったんですか。スラチャイさんを先に決めてると思ってました。
富田「でね、実はもう一人候補がいたんですよ」
――もう一人?
富田「ポンシット・カンピーに出てもらおうと思ってたんです」
――それはここで喋っていいんですか?
相澤「いいですよ。いいですよ」
富田「ポンシット・カンピーの楽屋へ乗り込んで行きましたから」
相澤「コンタクト取ったんですから、僕たち」
富田「ポンシット・カンピーがバンコクでコンサートをやったとき、控室にうちらの仲間が潜り込んだんです(笑)。シコウって言うんですけど、タイ語が堪能な地元の後輩で。実はこれまでの俺達の旅には、常にこのシコウが同行して通訳をしてくれていたんです。で、シコウがあるとき、「監督、僕、乗り込んで来ます!」って、ネクタイ絞めて、ポンシット・カンピーのライヴの控室に無理やりお願いして入りこんで、ポンシット・カンピーが目の前。シコウもカンピー・ファンだから」
相澤「カチカチです(笑)」
富田「カッチカチなんです。そんなこともあろうかと、一応、レジュメを作ってですね。ペラ1枚で、それをタイ語にして。どういう企画で、こういう役で、実はチット・プーミサックっていう人も出てきてみたいな。でも、ポンシットは国民的大スターだし、僕らの懐事情的にはチョイ役でのお願いだったんです(笑)。さっきの「田舎はいいね」がかかるショットで、ばぁ~って空撮で行くじゃないですか、で、下にサムローがビュ~って走ってるんですけど、そのサムローの運転手、ノンカーイでサムローを運転してるのがポンシット・カンピー。で、あの「君を買い戻す」を歌うライヴ・シーンのあそこでポンシット・カンピーが自身の「君を買い戻す」を歌っている。昼間はサムロー運転手、夜はあのパブでライブする地元のミュージシャン。しかもポンシットはノンカーイ出身なんで、これで決まりだと勝手に思い続けていました。笑」
――その絵はキますね!でも、残念ながら……。
富田「そう、それでシコウがそのレジュメを渡して「興味ある」って言ってくれたんです、最初。シコウが興奮気味に帰って来て「監督、いけるかもしれないっっ!!」って。でも待てど暮らせど返事が来ない(笑)。シコウに「ちょっと電話してみようぜ」つって、俺の目の前でマネージャーの人に電話したら、「ま、無いね!」(爆笑)と、あっさり」
――幻の名シーンでしたね。
相澤「そうですね、そんなわけで」
富田「その後、スラチャイさんに……」
――カラワンのリーダー、スラチャイ・ジャンティマトン。ポンシットよりさらに大物にアタック。
富田「スラチャイさんに直接、お話をしに行った時に聞いてみたんです、スラチャイさんからポンシットに言ってもらったらどうか。「おい、弟子よ、お前、なんで断ったんだ、あの話」みたいになるかなぁ?と(笑)。そしたら「あ、ポンシットは無理」とあっさりスラチャイさん。「あいつはもう、売れ過ぎちゃってるから無理だ」って(笑)」
相澤「だから、スラチャイさんの時は、豊田勇造さんに会いに行って、豊田さんがちょうどタイにいる時だったから、スラチャイさんのところ行く時について行って、一緒に紹介してもらって」
――豊田勇造さんは80年代にカラワンを日本に呼ばれた有志の方で、京都の方ですね。
富田「豊田さんとつながったのは、豊田勇造ライヴ@マンダラ2に虎ちゃんが乗り込んで行って、最前列で歌ってたら、なんだお前ステージに上がれって。豊田勇造ライヴでいきなりコーラスをさせられた、っていう。そこからです」
相澤「なんかもう、この段階では基本的に当たって砕けろ戦法。笑」
富田「日本とタイで分かれて同じ戦法でやってたというわけです。笑」
相澤「言ってみようぜぇ、って。心臓バクバクで豊田さんにシナリオお渡ししました」
――スラチャイさんをチット・プーミサックの亡霊役にしたのは、僕はね、ひょうたんから駒で、でも結果的に最高で、好意的に取りましたけど。あれはもう凄く重要で、ある種の痛烈な皮肉ですよね。
相澤「アピチャートポンが同じ事、言ってました」
(※アピチャートポン(・ウィーラセータクン)はカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞したタイの映画監督で空族の支援者。念のため)
――その凄い皮肉な感じが、ぐじゃぐじゃでいいんじゃないですか。タイっぽい彩を与えているような感じもあって。タイ、ほんとややこしいからね。政治。
相澤「本当、そうなんですよね」
――なんか、転向しちゃったりするでしょ?よく分かんなくなる。スラチャイさんみたいにね。
富田「それはアピチャートポンがまさに指摘してて。どうなんだ?お前、どう思ってるんだ?これはバンコクで上映の暁には、みんなでディスカッションしなければならないところだ!ってね」
相澤「スラチャイさんは、昔の自分として出たんだ」
――スラチャイさん、当然、今も有名人ですけど、たぶん、昔とは全然……。
相澤「グラミーのせいなんじゃないですか。笑」
(※注:グラミーは現在タイ最大手のレコード会社。80年代に中央タイ・保守層ウケの音楽を出すレーベルとして発足)
――グラミーも節操ないんすよね。どっちなのって。でも、基本的にはお金儲かったら何でもしますよね。
相澤「あん時の、2回目の赤のデモじゃない時にいっぱいプア・チーウィットのミュージシャンが出てて、みんながみんな転向してっちゃってという話も聞きました」
――このへんのことは例の本(『TRIP TO ISAN: 旅するタイ・イサーン音楽ディスク・ガイド』Soi48編著、DU BOOKS刊)に書いたんで、機会があったら読んでみてください。あの辺りの事情、なんでああいう風になったかって、ぱっと音楽聞いてもわかんないわけですよ。
富田「ぜひ読みます」
――スラチャイさんについては、この演出が結局一番良かったんじゃないですか?
富田「「昔の自分の亡霊を演じているという皮肉なんだと俺は捉えたぞ」ってアピチャートポンは言ってました」
=終=
(Special thanks: 麻生学)
————————————————————————————————
空族(くぞく):
映像制作集団。2004年、「作りたい映画を勝手に作り、勝手に上映する」をモットーに『空族』を名のりはじめる。常識にとらわれない、毎回長期間に及ぶ独特の制作スタイル。配給、宣伝も自ら行ない、作品はすべて未ソフト化という独自路線をひた走る。テーマは日本に留まらず、広くアジアを見据えている。公式サイト:http://www.kuzoku.com/

©Bangkok Nites Partners 2016
富田克也:
1972年山梨県生まれ。2003年発表の処女作、『雲の上』が「映画美学校映画祭2004」にてスカラシップを獲得。これをもとに『国道20号線』(’07)制作・発表。『サウダーヂ』(’11)ではナント三大陸映画祭グランプリ、ロカルノ国際映画祭独立批評家連盟特別賞を受賞。国内では高崎映画祭最優秀作品賞、毎日映画コンクール優秀作品賞&監督賞をW受賞。フランスでも全国公開された。最新作はオムニバス作品 『チェンライの娘 (『同じ星下、それぞれ夜より』)』(’12)

©Bangkok Nites Partners 2016
相澤虎之助:
1974年埼玉県生まれ。早稲田大学シネマ研究会を経て空族に参加。監督作、『花物語バビロン』(’97) が山形国際ドキュメンタリー映画祭にて上映。『かたびら街』(’03)は富田監督作品『雲の上』と共に7ヶ月間にわたり公開。空族結成以来『国道20号線』(’07)、『サウダーヂ』(’11) 『チェンライの娘』(’12)と、富田監督作品の共同脚本を務めている。自身監督最新作はライフワークである東南アジア三部作の第2弾『バビロン2ーTHE OZAWAー』(’12)。